 宅建業法
宅建業法 宅建業法第37条書面を電磁的方法で交付する場合の注意点
宅建業法第37条書面とは、厳密に言うと「契約書」とは異なりますが、一般的に契約書と37条書面を兼ねている場合がほとんどです。デジタル化がすすみ不動産に関わる各種の契約においても、ITを活用するシーンが多くなっています。ここでは、37条書面を...
 宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  宅建業法
宅建業法  民法
民法 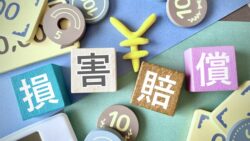 民法
民法  民法
民法